◆その日がやってきた。
家に帰ると、入学式に着たジャケットをタンスから取り出した。 洗面場の鏡の前でポーズをとってみる。 どこかスッキリしない。 親父のタンスからネクタイを取り出し、また鏡の前に立ってみた。
「これでいい」 鏡に映った自分の姿に満足し、笑みがこぼれた。 しかし、ネクタイがうまく結べない。
ネクタイと格闘していると、いつのまにか鏡の中に母の心配そうな顔が映っていた。
「何しているの」
「ネクタイが結べなくって」
「あら、お父さんのネクタイじゃないの。しょうがないわね。こっちを向いて。しゃがんで」
母はブツブツと文句を言いながらも、きっちりとネクタイをつけてくれた。
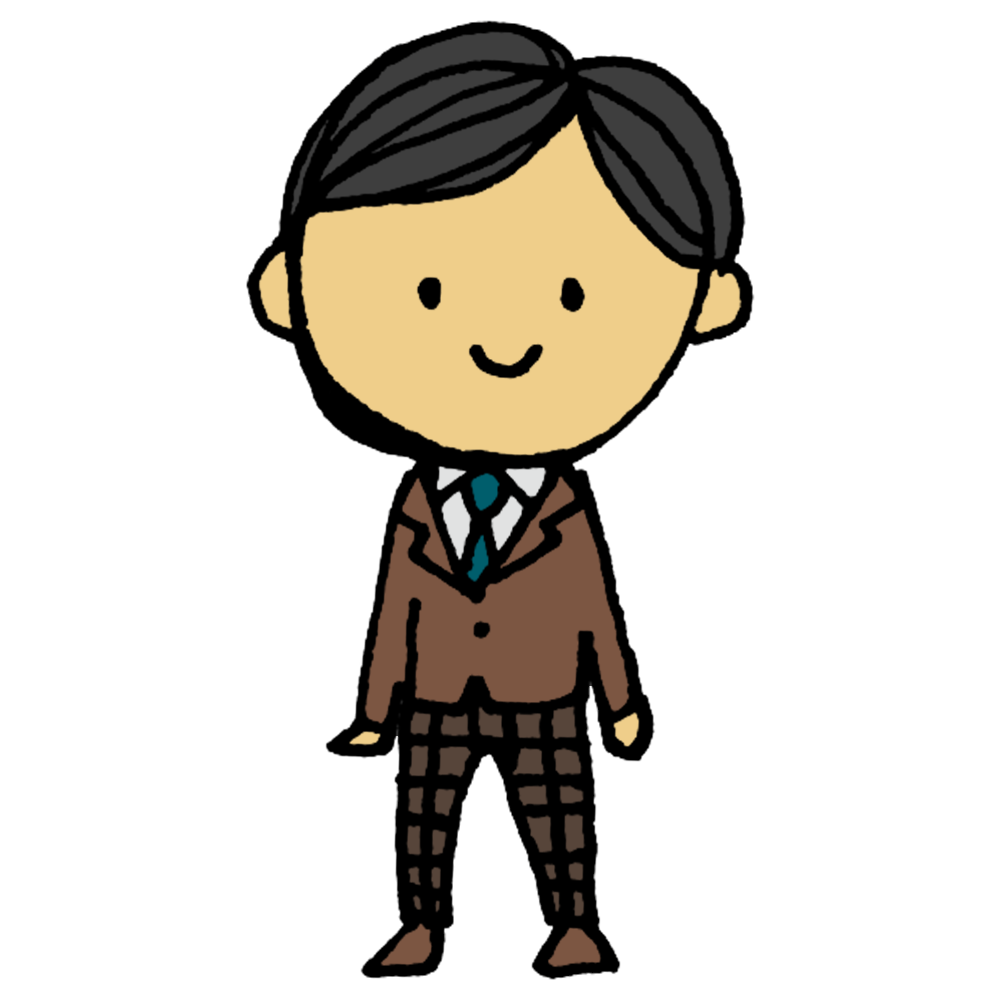
「どこに行くの」
母にダンパの事は話していないので、突然オシャレをしている自分を不思議そうに見つめた。
「ち、ちょっと部活の正式な会合があって」
どもりながら、横を向いて返事をした。
そのとき、二階から姉が降りてきて大きな声で叫んだ。 「こんな時間にネクタイをつけて行くのはダンパしかないって」
2歳年上の姉は女子大に通っているので、事情はよく分かっている。
「ダンパってなに。変なとこに行くのじゃないでしょうね」
母が心配そうに尋ねた。
声が出ない。 顔が火照っている。
「大丈夫よ、女子大生にチケットを売りつけて、ホテルでダンスをするだけ」
姉がかわりに答えた。
「ダンスって、出来るの」
「出来るわけないじゃん。格好だけよ。大体、こんなガキまともに相手にしてくれないわよ」 いつもの毒舌が飛んだ。
「うるさいな」
それだけを言うと逃げるように家を走って出た。
◆ホテルに着くと早速受付の設営をさせられた。

「北岡と川口は受付をやってくれ」
先輩はそういうとホールに入って行った。 机を出して、その上にチケットを入れる箱とチラシを置く。 チラシにはスキー部の紹介と冬に開催するスキーバスの案内が書いてある。
暫くすると外で車が止まる音がした。
「準備は出来たか」
先輩の声に「ハイ」とみんなが声を揃えた。
扉が開くと、色あでやかなドレスを着た女子大生が次々と入って来た。
同時に入り口のロビーは艶めかしい香水の匂いが充満した。
先輩方がチケットを女子大に配ったおかげで、見たことのないほどたくさんの女子大生がやってきた。
よくこれだけ色とりどりの様々な格好をした女性がいるものだと驚いた。
大学に入ったとき、きれいな洋服を着た女子大生に胸をときめかせたが、それまで同年代の女性の服装というのは普段着かセーラー服しか見た事がなかった。
呆然と見惚れていると、いきなりチケットが目の前に出された。
慌てて半券を切り取って渡す。
女子大生は先輩達のアテンドで次々とホールに吸い込まれていった。 ホールの扉が開くたびに大音響の音楽が聞こえてくる。
先輩の話では殆どプロといって良いくらい大学では有名なバンドらしい。
暫く音楽を聴きながら入場者のチケットをさばいていた。
突然野太い声が聞こえた。
「おい、預かってくれ」
突然偉そうな顔をした少し老けた男が女性をエスコートして入って来て、荷物を目の前に差し出した。
「お待ちしておりました」
その場を仕切っていた2年生の幹部が突然目の前まで走り出て、その手荷物を受け取ると自分に渡した。
その男性は4年生で元部長だったそうだ。
その男性は「ご苦労さん」と言って、女性の肩を抱くようにしてホールの中に入って行った。
◆1時間くらいすると、新たに来る者も殆どいなくなった。
「一人を残して、他は中に入って手伝ってくれ」
先輩の一言でみんながホールに入った。
ホールの中はバックミュージックが大きな音で流れていた。

「北岡、ちょっとこっちこい」
そういうと、ホールの壁の前でぼんやりと立っている一人の女性の前に連れていかれた。
(当時はそのような女性は<壁の花>といわれた)
「ウチの部の新人です。下手ですが、よかったらダンスの相手をしてくれませんか。こいつは一応ダンスが出来ますので」
普段偉そうにしている先輩が、その女性にやたら丁寧な口調で話しかけたのには驚いた。
昭和40年代当時の社会的風潮として、高校生でも男女共学とはいいながらも、圧倒的に「男尊女卑」だった。 高校の時、昼休みや放課後は男性は所狭しとサッカーや野球で校庭を犬のように走り回っていたが、女性は教室で静かに本を読んでいたり、校庭の隅でバレーボールをやっていた。 学園紛争のときの討論会でも女性は黙って固まっていた。 だから思春期になってからは、家族以外の女性と普通に話したことはなかった。
「よ、よろしくお願いします」
自分で顔が真っ赤になったのが判った。
女性は作り笑いを浮かべ、少し頭を下げた。
・・・こんなガキの相手か?・・・
と心の中で思っているのが透けて見えた。
それでも「一年生はチケットを売れないのだから、せめて女の子の相手をしろよ」という先輩の声を思い出し、その女性の手をとってホールの中へ向かった。
うす暗い中、点滅するミラーボールの照明でよく見えなかったが、ホールの中は体がぶつかり合うほど混んでいた。
多分5分くらい「ダンスらしく」手をとって体を動かしたが、およそダンススタジオで習ったようなステップは出来なかった。 どちらかというと、当時流行っていた「ゴーゴー(ダンス)」と変わらない動きだった。
音楽が止まり、小休止になった。 ドリンクをとって戻ったら、その女性はいなかった。
どう見ても<楽しい>という顔はしていなかった。
無論楽しそうに踊っている人たちも多かったが・・・・・・・・・。
◆暫くの間、音楽を聴きながら、みんなが踊っているのを眺めていた。
大学きっての生バンドの演奏は素晴らしかった。 当時当時大人気だった、ポールモーリアの「恋は水色」(恋はみずいろ ポール・モーリア L’amour est bleu Paul Mauriat – YouTube)、レーモンルフェーブルの「シバの女王」(シバの女王 レーモン・ルフェーブル La Reine de Saba Raymond Lefevre – YouTube)、パーシーフェイスの「夏の日の恋」(Percy Faith – Theme From A Summer Place – YouTube)などの艶やかなメロディが次から次にかかり、その音楽に酔っていた。
「北岡、そろそろお開きだから、受付に戻ってくれ」
突然先輩の声が聞こえた。
慌てて受付に戻り、やがて出てきた女子大生に預かっていた番号札と引き換えに手荷物を渡した。
3,4年生は着飾った女性の手をとって出てくると、女性の荷物を受け取り、外で駐車係に車をもってこさせ、女性と一緒に出て行った。
まるで外国の映画に出てくるような光景だった。
先輩達が出て行くと、後には疲れ切った表情の1,2年生だけが残っていた。
-1-pdf.jpg)
-pdf.jpg)

-1-pdf.jpg)

コメント